| 宮流神楽 曲の解説 前の曲へ 次の曲へ | 上のページへ トップページへ |
| 唐古・からうた・下がり葉・唐子の研究 | |
はじめに
幸村元一
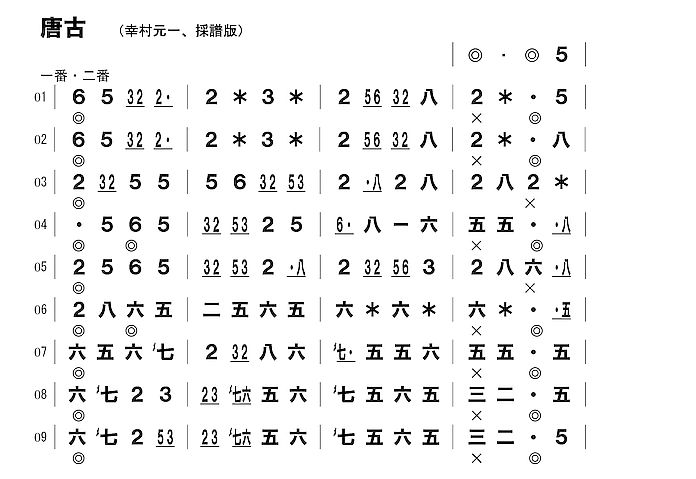 長谷川佐一
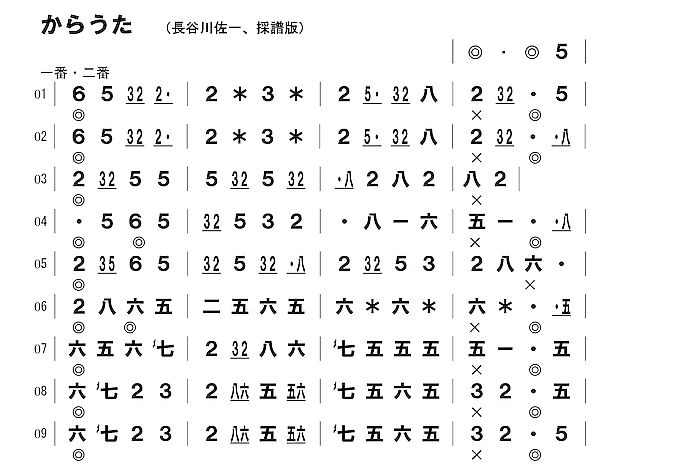 安東和雄・文雄
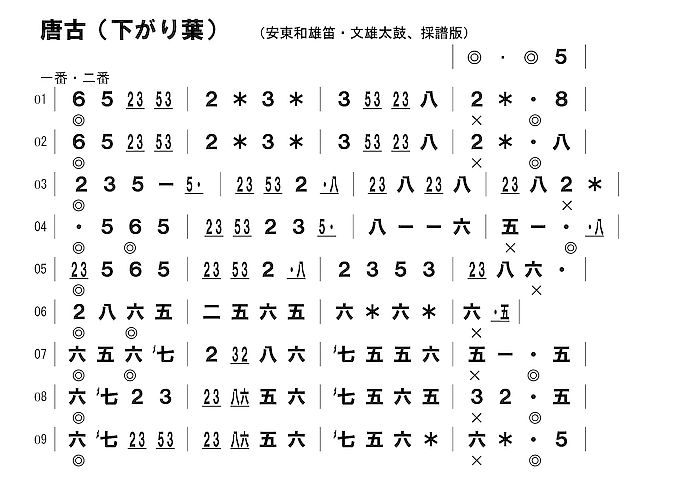 間瀬版楽譜
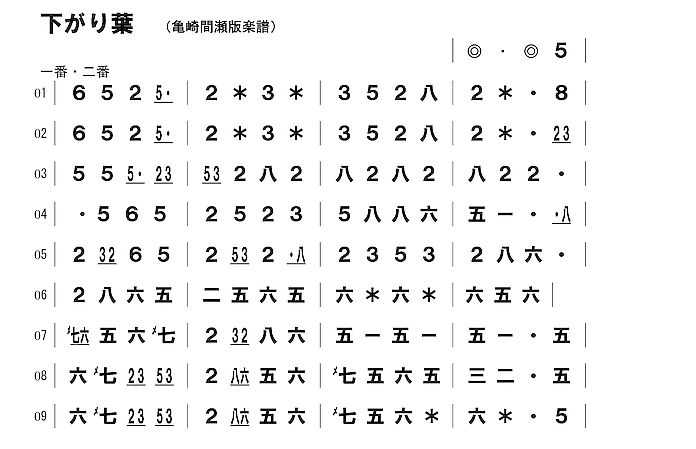 新亀崎版
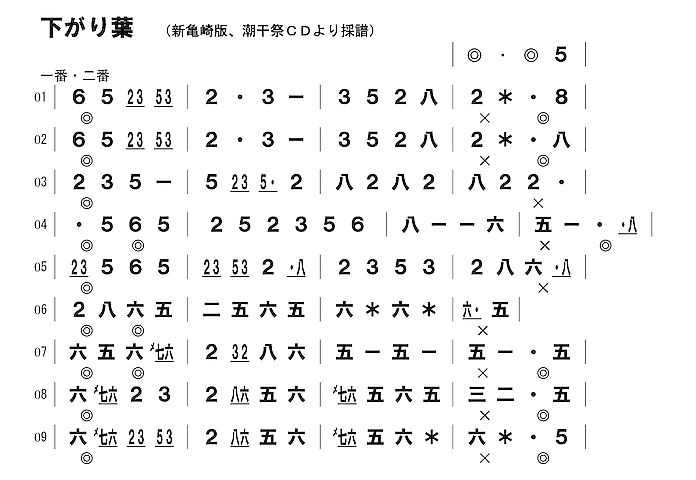 熱田神楽笠寺版
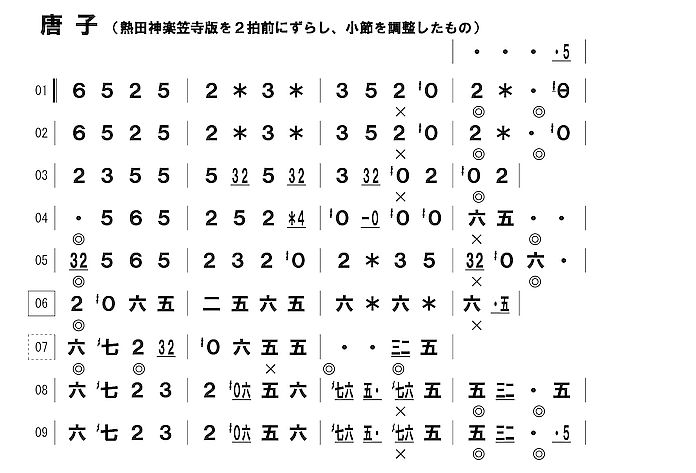 最後に
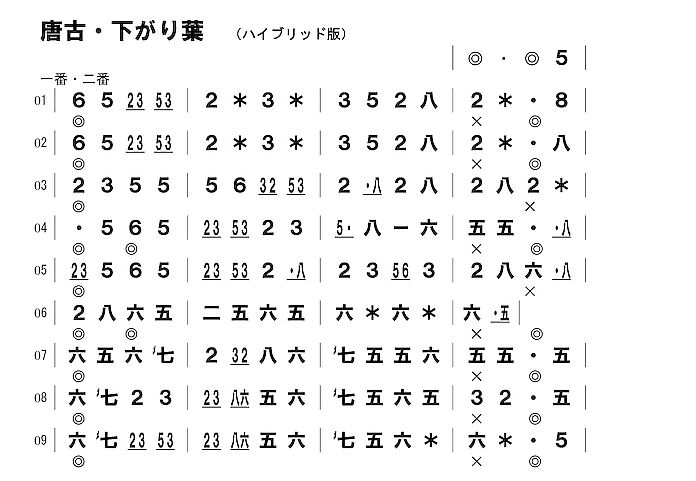 |
| トップページに戻る | 上のページに戻る | メールを送る | ||
| 宮流神楽 曲の解説 前の曲へ 次の曲へ | 上のページへ トップページへ |
| 唐古・からうた・下がり葉・唐子の研究 | |
はじめに
幸村元一
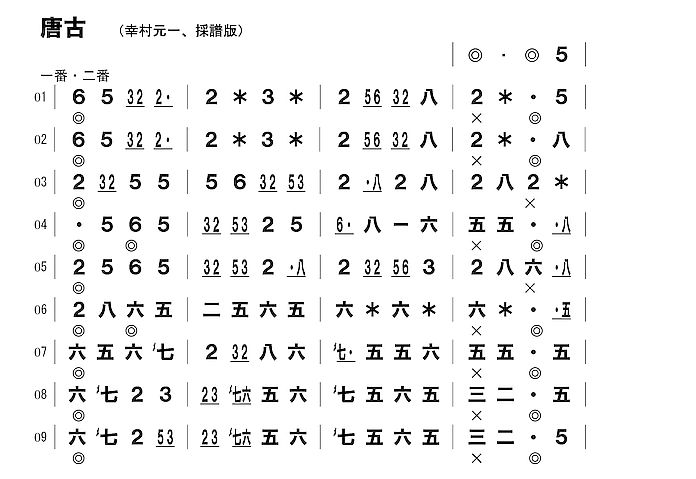 長谷川佐一
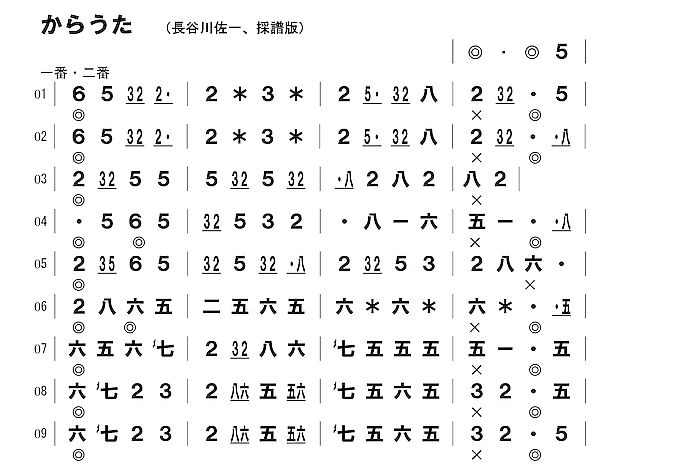 安東和雄・文雄
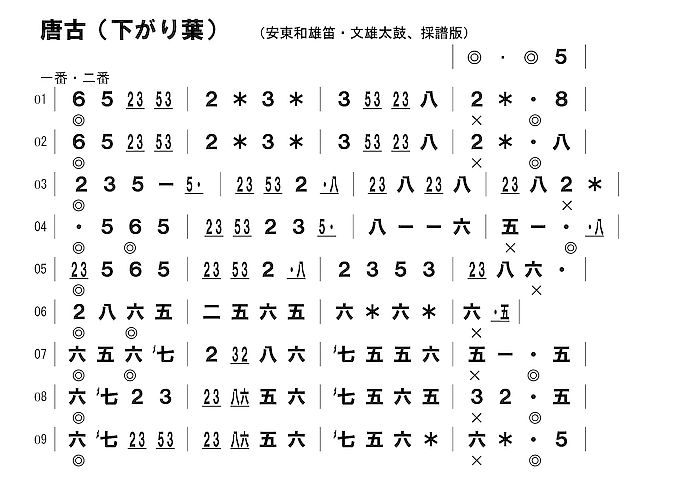 間瀬版楽譜
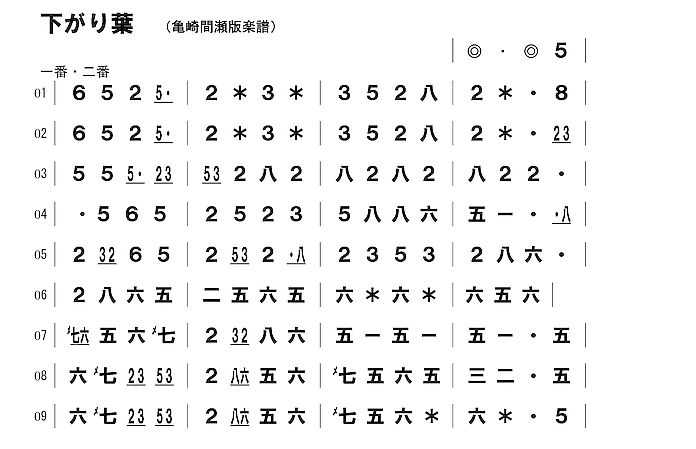 新亀崎版
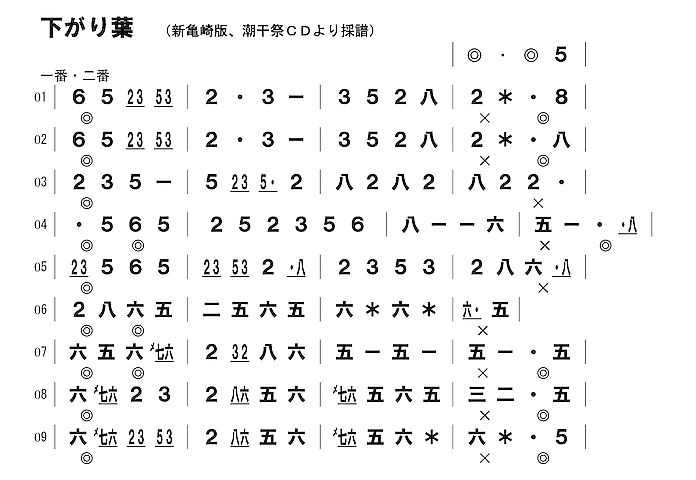 熱田神楽笠寺版
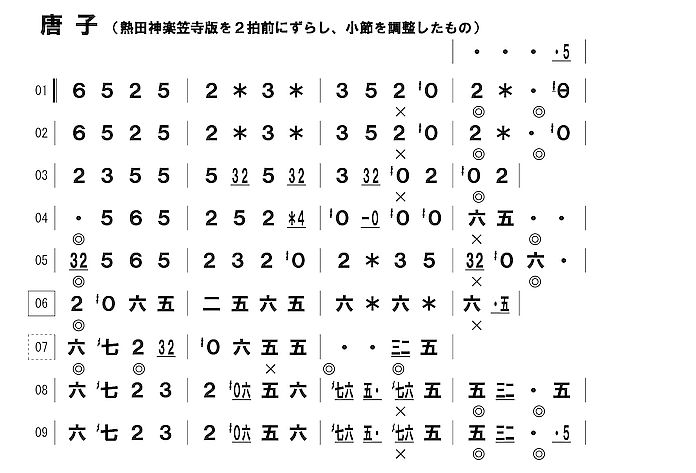 最後に
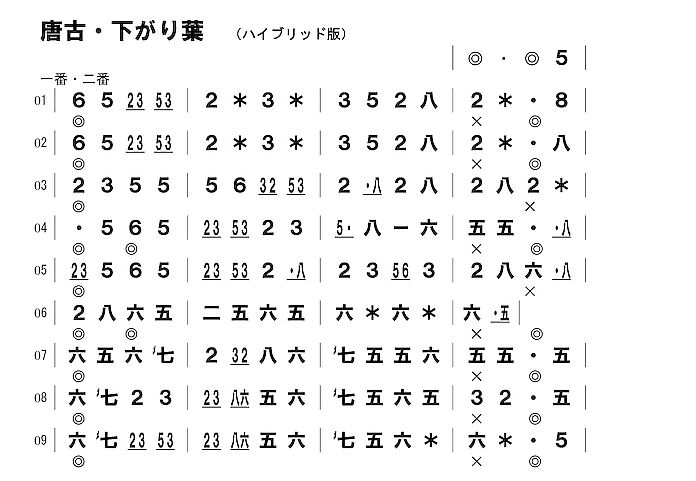 |
| トップページに戻る | 上のページに戻る | メールを送る | ||